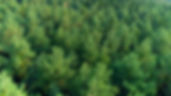時を超えて輝く 明珍の兜
- atsux.
- 7月13日
- 読了時間: 3分
更新日:8月3日
「散歩道」ブログにようこそ!
今回は、上野の国立博物館にやってきました。

国立博物館は、国宝や重要文化財に指定されている刀剣や太刀を鑑賞することができるので、刀剣女子だけでなく海外からの人にも人気です。
長船長光や正宗の名刀に出会い、しばしそこに凝縮した作刀精神と対話することができます。

しかし、今回ご報告するのは刀ではありません。改めて見入ってしまった、紺糸縅筋兜(こんいとおどしのすじかぶと)についてです。それは、明珍家17代目の甲冑師(かっちゅうし)「明珍信家(みょうちんのぶいえ)」の手によるもので、前立(まえだて)に菖蒲(しょうぶ)があしらわれた、なんとも美しい兜です。天文二年(1533年)に製作されたことが、裏の銘に刻まれているそうです。

【明珍とは?】
「明珍(みょうちん)」という名を聞いて、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。明珍家は、平安時代から続く甲冑師の家系で、特に戦国時代から江戸時代にかけて、その鉄を操る卓越した技術で名を馳せました。刀剣の切れ味を支える「鍛造(たんぞう)」の技術を甲冑に応用し、しなやかで堅牢(けんろう)な、それでいて美しい甲冑を生み出したことで知られています。その技術は、まさに匠の技(たくみのわざ)と言えるでしょう。武田信玄が着用した諏訪法性の兜(すわほっしょうのかぶと)も明珍信家の作です。
【菖蒲に込められた願い】
さて、この兜の最大の魅力は、やはりその前立でしょう。力強く束ねられた鯨の髭製(くじらのひげせい)の菖蒲が、兜の正面に威厳をもってそびえ立っています。
菖蒲は「勝負(しょうぶ)」に通じることから、武士にとっては縁起の良い植物とされてきました。また、その葉の形が剣に似ていることからも、尚武(しょうぶ)の精神を表すモチーフとして好まれました。
この兜を身につけた武将は、ひたすら、世の中の平和と、事が起こってしまった時の武運(ぶうん)を願っていたに違いありません。
【繊細さと力強さと機能性の融合】
明珍の作品は、その堅牢さの中に、驚くほどの繊細な美しさを秘めています。この菖蒲の前立も例外ではありません。鯨の髭という素材をここまで巧みに加工し、まるで本物の菖蒲が風になびいているかのような躍動感を表現しているのには、ただただ感嘆するばかりです。
兜全体を彩る紺色の威し糸(おどしいと)との対比もまた見事。静謐で剛健な紺色の中に、菖蒲の力強い存在感が際立ち、全体のバランスが絶妙です。鳶口型(とびぐちがた)の面具も実際の戦闘には不可欠のものでしょう。極めて機能的です。
【歴史を今に伝える至宝】
東京国立博物館に展示されているこの明珍の兜は、単なる歴史的遺物ではありません。それは、時代を超えて受け継がれてきた日本のものづくりの精神と、戦乱の世を生き抜いた武将たちの願いや美意識が凝縮された、まさに至宝と言えるものではないでしょうか。
博物館を訪れた際には、ぜひこの明珍の菖蒲の前立の兜に注目してみてください。その細部に宿る職人の魂と、込められた武士の想いを肌で感じることができるはずです。
それでは次回またお会いしましょう。